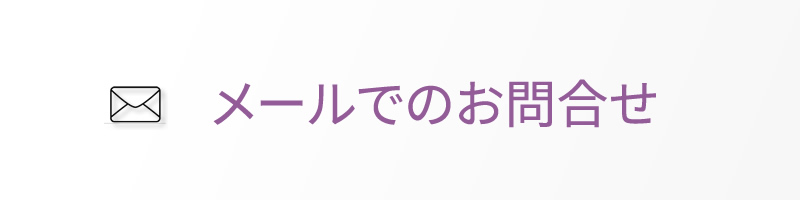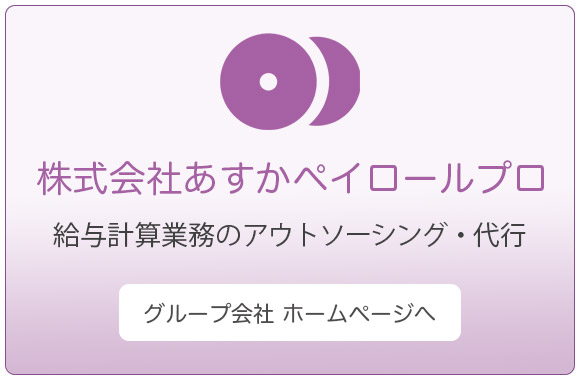労務の知恵
-
「グッドキャリア企業アワード」受賞企業の取組事例-厚生労働省-
◆キャリア形成・能力開発の重要性社会情勢・雇用環境が変わるなか、労働者一人ひとりが自身のキャリア形成を自律的に行うことが重要になっています。また、従業員のキャリア形成や能力開発を支援することは、採用強化・定着・離職防止の観点からも、事業主にとっても重要です。
続きを読む -
就職氷河期世代の就業等の動向と支援の今後の方向性について ~内閣官房 就職氷河期世代支援推進室のリーフレットより
◆就業の動向就職氷河期世代支援策の進捗状況として、2023年の就業動向を2019年との比較でみると、正規雇用は8万人増、役員13万人増で、合計21万人増の996万人となりました。不本意非正規は9万人減、非労働力人口は30万人減で、合計39万人減の217万人となりました。
続きを読む -
東京都がカスハラ防止指針を公表しました
◆東京都のカスハラ防止指針カスタマー・ハラスメント(以下、「カスハラ」という)の防止を目的に、昨年10月に東京都が全国で初の条例を公布したのは記憶に新しいところです。
続きを読む -
外国人技能実習生の転籍要件が明確化されました
◆技能実習の運用要領を改正出入国在留管理庁が、外国人技能実習の運用要領を改正し、転籍を可能とする場合の要件に、「ハラスメントを受けている場合」が明記されました。技能実習生の失踪の増加や、外国人労働者に対する人権侵害に対する批判が国際的にも高まっていることを受けた対応だと思われます。
続きを読む -
ハローワークにおける求人不受理の対象が追加されます
◆ハローワークにおける求人不受理の対象とは?ハローワークの求人は、労働関係法令の規定に違反し、企業名公表等の措置が講じられた者からの求人の申込みについては受理しないことができると、職業安定法の政令に規定されています。
続きを読む -
「就活セクハラ」防止義務化に向けた動き
◆「就活セクハラ」とは「就活セクハラ」とは、従業員間ではなく、就職活動中の学生に対して採用担当者等により行われるセクシャル・ハラスメントを指し、問題視されています。これまで、大企業を中心として、性被害などの深刻な事案も発生しており、自主的な指針を作る企業もみられます。
続きを読む -
立ち作業の負担軽減対策
◆立ち作業による体への負担工場のライン作業や、工事現場における交通誘導作業、スーパーの会計作業など様々な場面で見られる「立ち作業」は、業務に集中しやすい、とっさに動きやすいといったメリットがある一方で、長時間持続的に行われると足腰等への負担が大きくなり、作業効率も落ちるといったデメリットもあ...
続きを読む -
最低賃金の引上げと企業対応 ~労働政策研究・研修機構「最低賃金の引上げと企業行動に関する調査」より
◆過去最高の引上げ額となった今年の最低賃金今年も10月以降、各都道府県にて新しい最低賃金が適用されています。今年の全国加重平均額は1,055円となり、前年から51円引き上げられ過去最大の引上げ幅(引上げ率5.1%)となっています。
続きを読む -
マイナ保険証の利用登録の解除について
◆マイナ保険証の登録は解除できる12月2日に迫った現行の健康保険証の廃止とマイナ保険証への一本化に伴い、マイナンバーカードを取得していない方やマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方などには、保険者から資格確認書が交付され、それを医療機関に提示することにより、これまでと...
続きを読む -
就活中の学生の88%が「企業のSNSを見て入社意欲が増した」と回答 ~株式会社リソースクリエイションの調査から
SNS採用マーケティング「エアリク」を運営する、株式会社リソースクリエイションは、2025年卒業予定の就職活動中の学生575名を対象に、「SNS就活についての実態調査」を実施しました。その概要を紹介します。
続きを読む -
仕事より余暇を重視する割合が年々増加 ~日本生産性本部の調査より
◆「仕事より余暇を重視」する傾向日本生産性本部が「レジャー白書2024」(速報版)を公表しました。これは、余暇活動に関する個人の意識や参加実態に関するアンケート調査の結果をまとめたものです。この調査により、仕事よりも余暇を重視する人々の割合が年々増加していることが明らかになりました。
続きを読む -
賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)より
◆監督指導結果のポイント1 令和5年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は以下のとおり。
続きを読む -
令和7年4月施行の「65歳までの雇用確保の義務化」、認知度は約6割 ~エン・ジャパンのアンケート調査より
高年齢者雇用安定法による65歳までの雇用確保義務の経過措置は、2025年3月に終了します。2025年4月からは、65歳までの「定年引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年廃止」のいずれかの雇用確保措置が全企業の義務になります。
続きを読む -
受動喫煙防止対策助成金 令和6年度の申請が始まりました
◆受動喫煙防止対策助成金とは中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的とするものです(令和6年度の申請は令和7年1月31日まで)。
続きを読む -
たかが…、されど、やっぱりOJT
企業の力を高めるために若手社員の教育やOJTの必要性を感じながらも、うまく取り組めている自信がないという方も多いでしょう。HR総研が昨年実施した「若手社員の育成に関するアンケート調査」によると、中小企業で若手社員の育成計画を作成できている企業は53%しかないそうです。
続きを読む -
「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」が策定されました
厚生労働省は、事業を行う者のうち労働者を使用しないものおよび中小企業の事業主または役員(以下「個人事業者等」という。)が、労働者と同じ安全衛生水準を享受すべきであるという基本的な考え方のもと、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を策定、5月28日に都道府県労働局長に通達を出しました。
続きを読む -
食事の現物給与の価格が変更されました
◆現物給与とは?給与は金銭で支給されるのが一般的ですが、住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券などで支給することがあります。この場合、現物給与といいます。
続きを読む -
「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」のポイント
厚生労働省の「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」が策定・公表されました。本手引きに沿って、求職者等が求める情報と、企業が情報提供にあたって注意すべき点をみていきましょう。
続きを読む -
ワーケーションの実態と効果
パーソル総合研究所の「ワーケーションに関する定量調査」によると、普段の職場や自宅とは異なる日常生活圏外の場所で、仕事(テレワーク)をしながら自分の時間も過ごす「ワーケーション」や、出張先などで滞在を延長して余暇を過ごす「ブレジャー」を行ったことがある就業者は、17.4%いるそうです。
続きを読む -
花粉飛散量が「極めて多い日」はテレワークの検討も
◆表示ランクを30年ぶりに改定日本花粉学会は昨年12月、花粉飛散量の表示ランクを30年ぶりに改定し、これまでの「非常に多いと」いうランクを1日1平方センチあたりのスギ・ヒノキの花粉数50個以上から100個未満に改訂し、新たに100個以上の日を「極めて多い」とすることとしました。
続きを読む -
政府の少子化対策をまとめた「こども未来戦略」が決定されました
政府は12月22日、少子化対策をまとめた「こども未来戦略」を閣議決定しました。今後3年間の集中的な取組みである「加速化プラン」には、「共働き・共育ての推進」が盛り込まれています。具体的な内容は次の通りです。
続きを読む